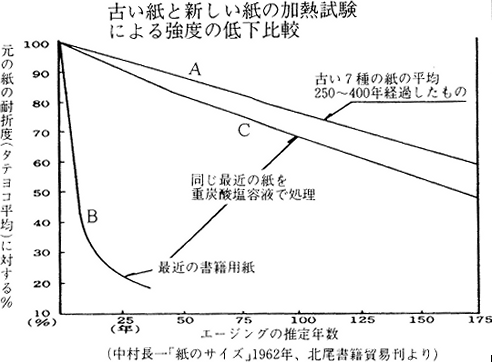スタッフのチカラ サブメニュー
スタッフのチカラ
【寄稿】永く残る本を — 書籍用紙の耐久性問題を考える —1983年金谷博雄
1. 不可思議な表示
米国議会図書館の「本のためのセンター」が編集した『アメリカの本の社会の責任』(「Responsibilities of the American Book Community」議会図書館刊、1981年)という本を、友人から手渡されたのは昨年(1982)春のことだった。コングロマリットによる大出版社の買収や、映画、テレビなど他媒体との”同時封切”などによるブロックバスター的企画の出現などで揺れる同国の出版事情にあって、これを率直に世論に問うために動き、成功したのが、議会図書館の一部署である「本のためのセンター」(Center for the Book:責任者はJ・Y・コウル氏)であった。著者と出版社、出版社と書店、他のマスコミ媒体と出版、そして大出版社と小出版社……これらの矛盾対立を「本の社会」(Book Community)の危機としてとらえ、この危機がすなわち図書館の危機なのだという認識が「本のためのセンター」にはあった。出版資本の過当集中を訴えた著作家組合や書店組合と大手出版社との応酬を収めた上院司法委員会公聴会議事録をはさみ、前後数回の同センター主催のシンポジウムの内容を記録したものがこの『アメリカの本の社会の責任』なのであった。
私は試みに同書を訳し、『アメリカ出版界の意識』と訳題して望まれる方々にお頒けした。決して客観風のレポートではないが、それだけになまなましい当事者たちの本音が出つくしていると言っても過言ではないと思えた。そして、こういう活動や文書を国費でまかない、国の図書館の刊行物としていることに驚かない訳にいがなかった。もちろん、日本での事情と対比してのことである。
ところで、同書のタイトル・ぺ一ジの裏、刊記のあるぺ一ジの最上部の一行が、当時の私には何とも不可思議な一文なのであった。『本書は永続的/耐用的用紙に印刷されています』—-パーマネント/デュァラブル・ペーパー、とある。初めての翻訳に四苦八苦の身分では、とりあえずこういう不可思議な文章などどうでもいい、すっとばして行くしかない。その訳了直後に、ある縁によってまさにその用紙問題にとり組むことになろうなどとは、その時の私には露ほども考え及ばなかったのだ。
2. 21世紀にはボロボロに
間違いでなければいいが、日本で「用紙の酸性問題」が初めて伝えられたのは1979年2月、読売新聞「世界の論調」欄に紹介された『USニューズ&ワールド・レポート』掲載記事の引用である。題して「21世紀には読めなくなる?ボロボロ蔵書」。
—-アメリカの図書館はひたひたとおし寄せる危機に直面している。書棚の何百万という蔵書がぼろぼろになっているのだ。・・・問題は1850年以降に発行された書籍の粗悪な用紙と製本で、その寿命はわずか25年だ。湿気、光、大気汚染が本に悪影響を及ぼし、酸が紙を変色させ、頁をめくればぼろぼろになる。・・・・議会図書館では、1,800万冊の蔵書のうち三分の一にあたる600万冊は「傷みが激しく」一般に貸し出せば「修理不能」になる状態だ。・・・・ニューヨーク公共図書館やハーバード大学でも、蔵書の半分が危ないという。・・・・1850年以前に印刷された本には綿や麻の繊維で作られた紙や、動物の皮を処理した羊皮紙が使われていた。これらの紙は、ここ100年急速に普及した酸性のパルプ紙に比べて、環境の悪影響を受けにくい。・・・・図書館資源協議会やアメリカ図書館協会などの団体は、用紙の酸を中和させるための新技術導入をよびかけている。・・・・(一部底本から補訳)
この記事を私に教えてくれたのは、装幀家の栃折久美子さんだが、以来ほぼ4年間、私はそれを忘れてしまってはいなかった。とはいえ、大学図書館に働く数人の友人にこの問題についての海外資料の探索を依頼していた程度で、他には何もしないでうち過ぎていた。同記事の内容にしたところで、事の大きさ故にかえってそう大した進捗があろうとは夢想だにしなかった。だから前掲の一書にあった「本書は永続的/耐用的用紙に印刷されています」という表示が、この問題の最大の解決策としての成果なのだということに、すぐには想い到らなかったのである。
3. 紙の酸性化が元凶
昨年11月初め、私は『本を残す用紙の酸性問題資料集』という小冊子を自費出版した。A5判、47頁の本文に、私の個人誌『工房雑記抄』1~3号(総36頁)を付して500円で頒布した。心ある新聞雑誌編集者の尽力により2ヵ月足らずのうちに1,000部が私の手から放れて行った。
店に置いてくれたのは、東京・神田神保町の書肆アクセスだけである。ある大書店からは、定価が低すぎるという理由で断わられた。おかげでほとんどが私からの直送なので、この問題に関心を寄せられた数百の方々の名簿を、私は居ながらに入手することができた。
機械製紙がひろまったのは19世紀中葉のことであるが、実験的成功がなったのは、おそらくは1800年頃ではあるまいか。そしてこの近代的製法による紙が、それ以前の手漉紙(欧州の)と比べて劣化が著しいことについては、1829年、イギリスの出版人ジョン・マーリーが初めてその原因を明らかにしているという。イタリアのフィレンツェでのある調査によれば、14~17世紀の文書のpHは6.9~7.2であり、18世紀のそれは6.2、19世紀のものは5.4であったという。
pHは水溶液の酸性度を測る尺度で、強酸は1、中性は7、強アルカリは14である(水は7)。そして、用紙が中性であった14~17世紀のものは、酸性の18世紀の本よりずっと保存状態がよく、さらに酸性の強まった19世紀の本は、少なくとも中和化して保存する必要に迫られているのだという。こうして「世紀」を単位に物を見ることができていれば、1800年に開発された新技術による新製品の欠陥を、わずか29年目に指摘したジョン・マーリーのことも、むしろ当然と言えるのではあるまいか。
紙中に酸が残留するのは、サイズ工程でバンドを使用する近代の機械抄紙の特徴である。サイズを施さないと新聞用紙や吸取紙やティシュなどのように吸水・吸油性が高いものとなり、書籍用紙としては不都合である。バンドは定着剤で、松脂から精製したロジン・サイズや石油から合成したサイズ剤を紙の組織に定着させる役割を果すのだが、このバンドが紙を抄紙工程から製品に到るまで酸性にしている元凶なのである。酸性用紙が中性用紙に比べていかにもろいものであるかについては、グラフを参照して頂きたい。最近の書籍用紙が寿命わずか25年というのは、決して誇張でないことがおわかりいただけると思う。
4. 米ではすでに保存計画
さて、本の物理的な保存の問題にもっとも関心を抱いていたのは、当然のことながら図書館であった。欧米の本の修補界では1850年以降の古書は、そのまま裏打してはならず、まず本を解体し、一葉一葉をアンモニア希釈液に浸して紙を中性化し、これを乾かしてから再製本するのが常道となって久しい。だが莫大なお金と時間のかかるこの手法が現実的でないことは明らかで、次いでマイクロフィルム化が導入され、期待を担った時期があった。今日でも磁気ファイルに移し替える方法などは、この考え方—別の媒体への移し替え—のひとつであろう。
だが、これらは本を「本」として残すことから言えば、邪道のそしりは免れない。そしてそれ以上に、たとえば米国議会図書館でのマイクロフィルム化作業を行うべき本の量とは、1976年の時点で、1万1,500人/年という仕事量であり、今の態勢で行けばあと300年かかり、お金にして9,000万ドルという巨費が必要なのだという。そして日々収蔵する本が、遠からずこうした仕事の対象になるのだとしたら、これもまた「本の社会」の危機でなくて何であろうか。
1976年12月16、17日の両日、「全国保存計画」企画会議に60名の専門家を招集したのが米国議会図書館のD・J・ブーアスティン館長であり、「本のためのセンター」の前身ともいうべき同館『目的・機構・企画の改革本部』のJ・Y・コウル議長たちであった。
図書館人による本の保存運動には、すでに救済を待つしかない古書の大量・高速かつ低廉な脱酸処理技術の開発と、これから古書となるべき新刊出版物に中性用紙を使用させることとの二つのテーマがある。もちろんことの推移は、前者を探るに並行して後者の問題意識がおのずと誘発されて来た。前者についてはジエチル亜鉛ガスにより、本を解体しないでそのまま脱酸化する技術の開発へと進み、昨年はメリーランド州グリーンベルトにある米航空宇宙局(NASA)のゴダード宇宙飛行センター内の大型真空室に5,000冊の古書を並べてガスを注入し、約一週間薫蒸して酸を中和させるという実験を議会図書館の手で行っている。各種の技術特許を議会図書館は得ているようである。またカナダ国立公文書館では1975年以来、米イリノイ州の化学処理設備会社ウェイ・トゥ・アソシエーツのR・D・スミス博士が同種の実験を継続している。
5. なぜ「本を残す」か
後者の中性用紙開発については、議会図書館や図書館資源協議会が出版社・製紙会社・図書館保存担当者などを招待しての数次のシンポジウムと、バロウ研究所に委託した研究(メロン財団からの基金援助による)などを通じて、1980年には米国内で発行された上製本の四分の一強が中性用紙を用いるところにまで到っている。冒頭にあげた議会図書館発行の一書なども、そうした意味からみずから範を垂れたものと言うべきであろう。
ちなみに、昨年10月初めの日本の日刊紙にカラーの一面広告を載せた米フランクリン・ライブラリー(東京に営業所)の総革装『世界文学最高傑作・家宝版』予約募集の広告文によれば、「本文ぺ一ジの折丁は丁寧な糸とじで、用紙は酸の残溜がない特製紙で何百年もの耐久性があります」と言う。日本語の本だから組版はともかくとして、用紙の調達と印刷は本国で行うのであろう。そうした「家宝版」を今、日本の愛書家は毎月1巻(全50巻)、1万8,000円で入手しているのである。
本を残す、と言う。「読まれない本は残る—よく読まれる本は残らない、そういうものだ」と学者ブーアスティン館長はある会議の合い間の昼食会で語っている。「我々は文明を残すために今日ここに集まったのだ」という彼の会議開会のあいさつも、だからこそなおさらに共感をよぶのだ。読まれる本も読まれない本も、等しく永く残そうではないか、少なくとも14~17世紀の文書ほどには—後の世代にとっていずれが必要であるかを、我々が決めることはできないのだ。我々が古文書から蒙った恩恵を、後の世に返す手段はそれしかない、と語っているように私には聞こえる。
そして、著者・出版社・流通業者の問題も、関連産業の問題も、各々の個別サークル内部では解決できない問題が確実にあり、それこそが相互に共通の絆なのであって、したがって共同の理想を描けるのもそうしたもっとも困難な地平においてなのだと思う。現実の、あるいは10年そこそこの矛盾対立を克服しようという時にさえ、百年を越える単位で(すなわち我々の生を越えて)「本の社会」を見つめる視点をお互いがいくらかでも頒ち会えているか否かは、ことの処し方に偉大な差違を生じよう。
6. 真に衝撃的なのは
大した進捗もあり得まいという一抹の気休めのもとに放っておいたテーマも、気づいた時にはすでに第一幕が終っていた。知らぬは我が身ばかりなりであった。そればかりか、第一幕の前には、膨大な序章があるのであった。
『ライブラリー・リテラチャー』という図書館関係雑誌記事目録があるが、これの「紙」の項だけとってみても数頁にわたって「用紙の酸性問題」の記事索引があるのだ。たしかにこの10年程は極端に充実してきてはいるが、1956年にフォード財団の援助で図書館資源協議会が設立され、翌1957年6月、同協議会の活動としてW・J・バロウが古書の劣化の実態調査にとり組み始めた前後から、その成果は中性用紙開発に到るまで、連綿と綴られている。バロウはこれ以前、1940年代中期に自分の最初の脱酸処理法を開発している専門家なのだが、彼がひろく知られるようになったのは、1959年発表の次のような報告によってであった。すなわち、
「1900年から1939年の間に出版された本の40%がたいへん傷んでおり、それらはただふつうに扱われたとして1983年までには使いものにならなくなるだろう。」
「1900年から1949年の間に出版されたノンフィクションの本の印紙を物理的強度の点から見ると、あと50年以上もつと思われるものは、そのうちわずか3%しかない。」
ふり返って見るに、我々にとって衝撃的なのは、その調査結果もさることながら、こうした実態調査研究に力を注いでいた機関があったこと、否、米国人などからは歴史が厚いが故に神秘的とも言われる東洋のこの島国においては、そうした調査をする人も機関も皆無であるという現実そのものなのではあるまいか。「和紙」という世界に誇れる伝統をもつ日本が、なぜ「洋紙」の欠陥とその修正までも再び輸入しなければならないのか。考えてみれば、これ以上の不可思議はないはずである。
国立国会図書館の製本担当部署は、和本修補に3名、洋古書に2名の計5名、年間予算が合わせて3,000万円ということである。同館の書架を実見したある友人は、触れれば粉々になる洋古書が山積していた、と興奮を隠さなかった。私の小冊子の読者からは、「外国から買った古書で1890年頃の本を一度開けただけで、届いた時のままです。というのは開ければ紙がぼろぼろとこぼれ落ちてしまうからです」との便りをいただいた。近くは私自身も10年前に出た100部位の限定画集の用紙がすでに黄色いシミだらけであった。そして、国立国会図書館でも、用紙問題の海外情報には私など足下にも及ばぬ方々がおられる。だが私の作成したほどの簡便な資料集作りで彼らが取り組んだとすれば、3年位はかかるだろうという。「だから民間人がこういう形でやってくれるとありがたい」のだと言う。こういうことを聞く時ほど「衝撃的」なことはないのではあるまいか。さらにつけ加えれば、どちらの心ある新聞雑誌編集者諸氏も、なぜ私の勤務先である日本書籍出版協会の事務局がこれを出版しなかったのかと、私が臨むほどには私を問い詰めなかった。それが無駄なことだとすでに感じているからかも知れないが。
7. 用紙問題の国際性
こうした資料集を作ることができたのにはひとつの大きな理由があった。それは底本がほとんど公文書であったことである。『ユネスコ・ブレティン・フォー・ライブラリーズ』や議会図書館『インフォメーション・ブレティン』である。特に後者は克明な会議議事録を載せている。全米を動かす計画にあたっては、会議はやりっ放しでむしろ「代表者」の舞台裏の根まわしの方が重要というどこかの国のやり方では何もできないのであろう。様々な異論もあくまで論脈に位置づけて記録しているのである。彼らも50州、我が方も50都道府県位があるのだが、どうやら「お国」の規模がここでは左右しているらしい。ことこの問題に関しては、全米計画とは世界にのぼりつめると同等という配慮がキャンペーンの仕方に読みとれた(今はその弊害を言うまい)。
議会図書館の蔵書は国立国会図書館の3倍以上だが、これは各国のものをずいぶん買っているからでもある。したがって彼らが蔵書の脱酸処理の問題から新刊書の中性用紙使用の問題へと論題を進める際に提起された問いは、「合衆国の外での中性用紙の普及はどうしたらいいのか」ということであった。これに対する答えを紹介しよう。
「中性用紙を使うという行動を我々が起こすことによってしか、我国での憂慮の強く明白な証拠を示すことはできない。それこそが他の諸国での並行的な努力を喚起できるのだ。書籍や雑誌は一個の国際的な必需品である。一国における進歩からすべての国が利益を得るのだ。・・・・また、用紙の基準を作りあげる過程は本質的に国際性をもつ。その過程こそ、だんだんと世界中の製紙会社と出版社とがその基準を自発的に遵守するようになるための力となろう。」
日本の紙パルプ技術協会では昨年12月、機関誌で「中性抄紙の海外動向について」の記事を載せたところだ。紙は原木から製品の流通まで国際的なものである。この2月、京都では国際紙会議が開かれる。図書館資源協議会の有力委貝で紙店社長のシュロッサー博士が基調講演を行うために来日すると言う。日本人の紙を見る眼の貧しさが指摘されなければいいが、と思う。
8. 中性用紙こそ新媒体
売った商品がどういう生涯を送るものかを、製造側は知らなければならないし、知っている側は知らせる義務がある。近来の商品は何であれ修理の効かないものばかりで、作り捨て、売り捨て、使い捨てである。電球だって絶対(?)切れないものもできるのだそうである。だが、すぐ切れる電球を作らせている罪は消費者にもあろう。紙の場合、大きな製紙会社でさえ発売当時のサンプルを永久保存して定期的に経年試験を行うということすらやっていないというのだから驚く。
だが本の場合はまだ解決しやすい情況にあるのだと思う。買い手の側に、本は長持ちするものという意識がまだあるからである。著者だって、自分の本が現実には数十年の寿命だということを知っている人は、今は少ない。皆がそのうちに本とはそういうものさと思うようになってからでは、とり返しがつくまい。
良質のパルプを使用し、サイズの工程も中性化した中性上質紙は輸入に頼らないでも国産品が出ているのだから、長期保存型の本らしい本も今は可能なのである。そして、修理の効く製本ということもよく考えて出版をすれば、本から離れて久しい愛書家たちを呼び戻すことは必ずできると思う。ビデオやワードプロセッサーに背伸びをして手を出すよりずっと出版屋らしい「新媒体」が、この中性印刷用紙なのである。
長持ちする本を作っては商売にならない、などと言うほど企画の力量が衰弱してしまった出版人には、無縁の話ではあるが。