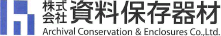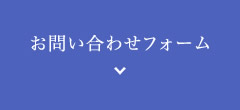今日の工房 サブメニュー
今日の工房
週替わりの工房風景をご覧ください。毎日こんな仕事をしています。
2025年9月26日(金)学習院大学大学院アーカイブズ学専攻の学生の皆さんと、保存修復の特別実習をおこないました
先日、学習院大学大学院アーカイブズ学専攻の皆さんをお迎えし、保存修復の特別実習を行いました。
同専攻では、学生が保存修復の基礎を体験的に学ぶ『アーカイブズ保存修復実習』を実施しており、今回は修士課程の学生と修了生あわせて8名が参加し、下重教授のご協力のもと、当社スタッフが終日指導を担当しました。少人数ならではの雰囲気の中で質問や意見交換を交えながら進めました。
午前:和紙資料の補修
虫損による損傷が著しい和書に対する補修について、まずは、虫損程度の違いにより適用する技術と材料の使い分けを紹介しました。サンプル和書を用いて、綴じの解体、本紙の展開、虫糞や付着物のクリーニングを行った後、補修用和紙と小麦デンプン糊を用いて部分的に虫損箇所を補填する繕いについて、解説を交えながらご覧いただきました。
続いて、同じサンプル和書の中から、虫損が全体に広がり取り扱いが不便な本紙に対して、和紙を用いた裏打ちや、漉き嵌め機による補填作業を体験していただきました。裏打ちは本紙の裏面に補助紙を貼って強度を高め、全体の安定性を得る方法で、大きな破れや構造的な弱さを補うのに有効です。ただし、厚みや硬さが増すことで手触りや透光性に変化が生じ、原本の質感が損なわれる場合もあります。
一方、漉き嵌め補填は欠損部を紙繊維で埋め込み、本紙と一体化させる方法で、境界の段差が目立たず、透光性や表面の表情も本紙に近い仕上がりとなります。その反面、繊維の漉き具合や乾燥管理など技術を要します。二つの方法を比較することで、仕上がりや触感、透過光での見え方など、条件の違いが質感にどのように反映されるかを体感していただきました。
午前後半〜午後冒頭:製本用素材の解説とリンプ製本の製作
午前後半から午後冒頭にかけては、製本の素材・構造・歴史について解説し、書物の形態をご紹介しました。題材に、中世ヨーロッパで広く用いられた「リンプ・ベラム(Limp vellum binding/リンプ製本)」を取り上げ、糸綴じから表紙の取り付けまでを実際に体験していただきました。
リンプ製本は、板紙を使わず柔らかい羊皮紙などで本文をくるむ簡素な構造を特徴とし、軽量で一定の強度を備えた装丁様式です。装飾的な豪華本や木板・厚紙で仕立てた装丁に比べて経済的かつ効率的であったため、16〜17世紀には学者や修道院で日常的に用いられ、現在も多くの実例が残されています(Foot 1993, Pickwoad 1995)。
一部では後に改装されるまでの仮綴じ的な使い方も確認されていますが、多くはそのまま廉価な実用装丁として長く使われました。こうした「簡素で負担が少なく、必要に応じて解体や再製本も容易」という特性は、現代の保存修復においても利点となります。1966年のフィレンツェ洪水では、英国の製本家クリストファー・クラークソンが被災書物の救済活動に参加し、伝統的なリンプ製本を調査・応用しました。彼はこれを保存修復に適した「コンザベーション・バインディング」として体系化し、国際的に広めました(Clarkson 1975, 1982)。そのためリンプ製本は、歴史的には廉価で簡素な装丁でありながら、今日では保存製本の基礎技法として位置づけられています。
• Clarkson, Christopher. Limp Vellum Binding and its Potential as a Conservation Type Structure for the Rebinding of Early Printed Books. 1975; revised 1982.
• Foot, Mirjam. Studies in the History of Bookbinding. Aldershot: Variorum, 1993.
• Pickwoad, Nicholas. Pickwoad, Nicholas, “The Interpretation of Bookbinding Structure: An Examination of Sixteenth-Century Bindings in the Ramey Collection in the Pierpont Morgan Library” 1995.
修理実習のおわりに
処置中の劣化した資料を観察しながら、素材や書写・印刷材料、記録方法の特徴を説明し、損傷の程度を解説しました。あわせて、お預かりの経緯や修理方針を紹介し、質疑応答を交えて進めました。保存修復の基本である「観察→判断→処置」の流れを確認し、部分的な補修にとどまらず資料全体を対象に課題を捉える方法を伝えました。
保存修復は補修だけで完結するものではなく、状態調査、修理方針の立案、ドライクリーニング、形態の安定化といった初期処置を経て、段階的に修理手順に移ります。今回の実習では、この流れを確認し、損傷の程度に応じて処置を選択する判断基準と基本的な考え方を共有しました。
午後:保存容器づくり
午後後半は保存容器の制作を行いました。採寸から展開図の確認、ボードの裁断、折り筋入れ、折り加工、組み立てまでを体験し、資料に合わせて仕立てる工程を学びました。保存容器は、補修と並ぶ予防保存の方法であり、箱やフォルダーといった容器が湿度、光、埃、機械的な衝撃などの外的要因から資料を守る役割を果たします。
「保存容器(enclosure)」という概念は、米国の製本家ヘディ・カイルが 「Library Materials Preservation Manual(1983年)」で示したことで広まりました。エンクロージャーは単なる箱や封筒ではなく、保護を要する資料を収める保存目的の容器を指し、現在では、preservation enclosuresの名称で保存分野の文献や資材カタログに広く定着しています。
ヘディ・カイルが考案した「カイル・ラッパー(Kyle wrapper)」は、一枚の厚紙を折るだけで冊子や薄い資料を包む簡易容器です。糊や金具を使わず短時間で作れるため、現場で一次的に資料を保護する方法として適しています。シンプルな構造の中に、資料を安全に包むという保存の考え方が形になっています。
• Kyle, Hedi. *Library Materials Preservation Manual: Practical Methods for Preserving Books, Pamphlets, and Other Printed Materials.* New Castle, DE: Oak Knoll Books, 1983.
実習では、参加された方々が熱心に取り組み、落ち着いた姿勢で学びながらも楽しむ様子がとても印象的でした。長時間に及びましたが、その熱意が自然と場をつくり、最後まで和やかな雰囲気の中で進みました。
破れや欠損の補修にとどまらず、素材や構造、劣化の広がりを踏まえて資料全体を見つめ、どのような処置や対応がふさわしいかを共に考える時間は、私たちにとっても貴重な経験となりました。